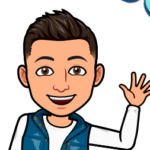386日目 あらゆる方向から事業を操縦せよ

一日作業も終わらぬ経費処理
2024年の1月から、領収書を順に確認をして、エクセルフォーマットに入力するという作業をほぼ一日通して実施をしていった。
7月まで入力が終わり、個人事業主としては10月が最終となるため、残すはあと3ヵ月なのだけれど、8月からは温調デバイスの製造関連の材料や工具やらが含まれてくるとので、3ヵ月とは言え少し時間がかかりそうだ。
ここまでの7ヵ月分を見ると、ほとんどが経費としての科目ばかりで「よくもまあ、何も受注をせずに動き回っていたな」と思うところである。
売上にしても10月の段階では150万円程度に収まる形で、経費の方が上回るから、事業としては赤字であることは変わりはない。
個人事業主の事業は、10月で法人登録をしたものの、資産等は何も移さず、赤字のまま開店はさせておこうと考えている。
法人と個人事業主の事業の差別化をどうするか等、いずれは決めていかなければならないだろうけれど、売り上げが上がっていないので、今は何も決めずに突っ走るしかない。
それはそうとして、やはりお金の出し入れを見える化しておくことは大切であることは、一つ一つの伝票を見て思い知らされた部分もある。
できていなかった月締めの整理も今月から実施していくようにしたい。
新たな刺激でがぜんやる気に
信用金庫の支店長の紹介で、近所の経営者に連絡を取ると、すぐに返事が返ってきて、さっそくオンラインで情報交換をしようということになっていて、その初顔合わせが今日の昼一に実施された。
思っていたよりも若くはなく、とは言え40歳手前ということもあって、同世代と言わせてもらうにはこちらが7つも8つも年上というところで恐縮であったが、とても刺激的な出会いをすることができた。
同じ機械設計出身ということに加えて、ほぼ同時に独立をした者同士ということは意識していたが、まずはこちらからこれまでの簡単な経緯と独立後にやっていることなどをざっとお話をすると、「すごく楽しい」「参考になる」なんて、コメントをしてくださった。
「そうだろう、そうだろう、売り上げは別にすれば、それなりに活動はしてきたのだ」と、一種の自負のような面が態度や言葉尻から出ていたかも知れない。
そして、あちら側は何をされているか、というところは、何となく想像は付いていて、「常駐で設計をやっているはずだ」と決めつけていたのだが、それは全くその通りであった。
しかし、その思いや将来的にやりたいと思っていることは、こちらの将来像と似ている部分もあり、そのために「早くキャッシュフローを安定にさせてやりたいことをやるのだ」という思考を持たれている方であった。
そして、現在の取り組みを聞いた時に、ハッとするのであった。
現在は、人を雇用して去年一年やってきたことを準委任として雇用者に託し、雇用を数人まで増やして、自分は設計から離れられるようにする、ということなのだ。
一年かけて、設計案件で何とか食いつなげるようになっているこちらがやろうとしていることを、いとも簡単に、そして次のステップに踏み出そうとしている、という点において、何とも計画性のない、行き当たりばったりのことをしていたのだ、と自分に言い聞かせることとなった。
準委任という形態もリモートワークが出てきたために、少々形をかえているようであるし、雇用と言ってもシニアを雇用しようとしている点においては、すごく興味深いところもある。
ライバルというにはおこがましいが、負けないように、そして共に成長できるように食らいついて行きたいと思わせてくれる方と出会えたことは感謝である。
思わぬ効果の開業日誌
このブログも1年が経過して、意味があることなのかと思いつつも、何とか続けられている状況だ。
意外な効果として気づかされたことが2点あるので、それを記載しようと思う。
一点目が、プラス面でもマイナス面でも高揚した気持ちが収まるということだ。
今日の出来事を夜のうちに3つピックアップしておき、翌朝に記事にしていくというスタンスを定着させているが、少し時間が空いて客観的にみられるという作用が働いているのか、文字にすることで気持ちが整理されるのか分からないが、感情を抜きにした記録とすることができるメリットがあるような気がする。
というのも、昨日に未収金となっていた伝票処理として、お客様に請求書を発行したところ、減額を要求されてほとほと困っていたのだけれど、記事にすることによって、「お互いに建設的になるような交渉をしよう」と冷静になって再請求をすることができるようになったからだ。
結果はうまくいくかは分からないが、自分としては腑に落ちる感じで対応ができたので、文字で考えを整理する手法の効果を確認できた出来事であった。
もう一点が、過去の履歴を追えるという点だ。
遡りで経費処理をしている際に、あれ、これはどこに行った時の領収書だろうか?と思うことが何件かあるのだけれど、その日の出来事を読み返すと、はっきり思い出すことができるのだ。
信ぴょう性という意味で、ブログが正当性を持つのかは分からないが、データを上書きすることもないし、少なくとも個人の記憶を呼び起こすには最適な面があると思っている。
できるところまで、この日誌は続けたいところだ。